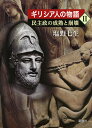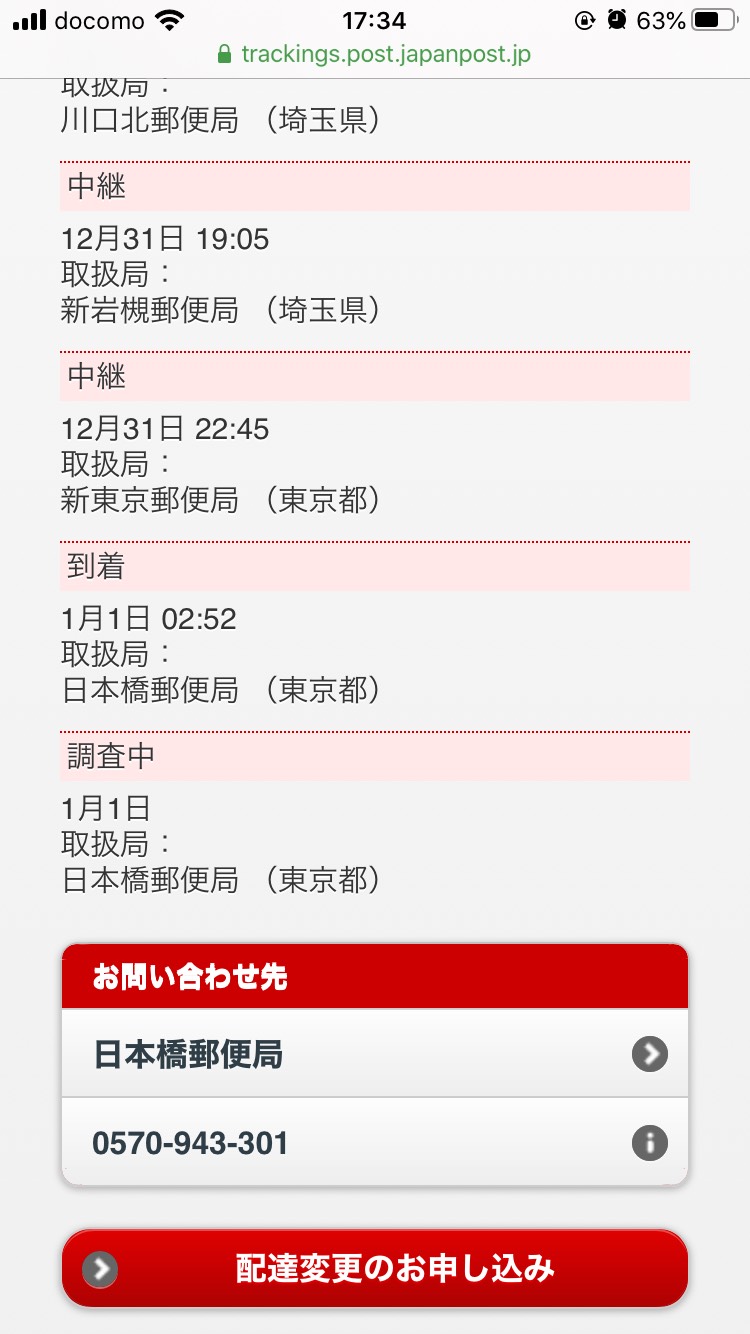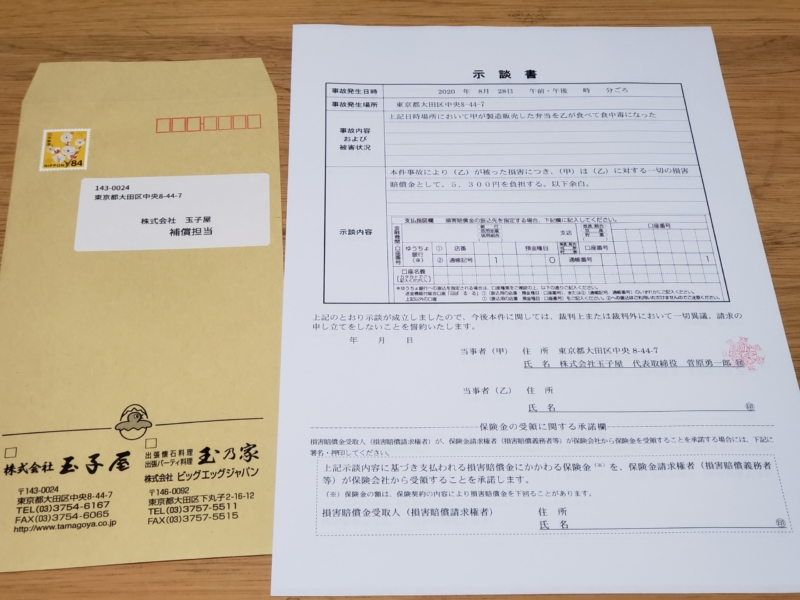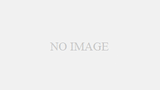2月の初旬、小泉進次郎氏が朝のワイドショー番組で出演された際に、正月休みに読まれた書籍として「ギリシア人の物語」を取り上げて、「3000円で古代ギリシアにタイムスリップ出来るのは、活字文化の凄さです」と発言したことが話題になり、その後、某雑誌では小泉進次郎氏とアレクサンドロスを比較する記事まで登場するとは、今ギリシアブームなのかなって思ったのですが、読むのが遅ければ、書くのも遅いのでこの時期になりました事、深くお詫びします!
『ギリシア人の物語Ⅲ 新しき力』 を読んで!
塩野七生氏の最後の歴史長編小説。帯にフレーズが有るというのは、これが最後著作なのでしょうか?
「十七歳の夏」のタイトルで珍しくエッセイを挿入してるので、信憑性は高いですが、その話は後に譲るとして!
前作までの1・2巻は、こちらをどうぞ!!


本編は、ギリシャ全土における覇権争い「ペロポネソス戦役」の終結により、アテネの凋落から始まり「そして誰もいなくなった」の言葉で有名な都市国家ギリシャの終焉、マケドニアの台頭、『アレクサンドロス大王』の東征、東地中海世界に巻き起こるヘレニズム世界の謳歌までを綴った長編小説。
「デロス同盟」はギリシャ世界に置いての、軍事同盟としての側面よりもアテネの主導の広域経済流通圏として、エーゲ海を我が物顔ように闊歩してたアテネは戦後、全ての地位も財も無くし、まるで時代の流れに逆らうこと無く没落の道へ転げ落ちます。勝者であるスパルタは対外政策を持ち合わせて無く、身分格差の固定から来る国全体の閉塞感が、そのままギリシャ全土に覆い包みます。その後、スパルタに勝ったテーベも勢力拡大に務めるのですが、道半ばで倒れ「そして誰もいなくなった」。
このギリシャ全土の混迷を1人の若きマケドニアの青年は我が身のように考え、マケドニアに戻って改革を断行したフィリッポス王。
本作は程よい距離感で話は進んでいきます。
ソクラテスの処刑も淡々と描かれていて、もし詳しく知りたければ、ソクラテスの関連の書籍をどうぞと、クレノフォンの敵中突破行も「アナバシス」をお読みくださいと言う感じで話は進んでいきます。
昔のようにいちいち説明するためにページを割く事は無く、淡々と描かれています。しかし、その時代背景を知りたいと興味を持つので、その著作を探し読む。まさにギリシャ史の入門書と言うよりも、本作が辞書のように次々と紐のようにギリシア世界の事柄を自分で調べていく導いていく著作であり、正に快作です。
そして好い男好きの塩野七生氏の描くアレクサンドロスの半生。「そして誰もいなくなった」ギリシア世界の閉塞感を理解しなければ、アレクサンドロスが如何にして人々に愛されたのかは理解出来ないでしょう。そういう意味では、本作がアテネの凋落から始まるのは、塩野七生氏の編制には感心します。英雄が起こす風は、時には穏やか、時には激しく、エーゲ海で巻き起こった風が東地中海からインドへと流れ、人々に記憶を残すのです。
民主政・寡頭政・王政の狭間!!
寡頭政か民衆政かで争ったギリシャ本土で、最後に勝ったのが「王政」とは皮肉と滑稽さを感じる。
民主政にしろ、寡頭政にしろ、最終的なリーダー(責任者)が不在になると、国の運営は混迷を極めて、長期的な視野に入れて一貫した政略を行う事もできず、ただただ人気取りの政策ばかりで責任を負う覚悟もなく、決定を市民集会に丸投げ、確かに実行に移す段階でも責任者が不明確ではさらに遅れる国の運営は混迷の度も増す。あの民主政の優等生だったアテネですら、この頃にはテミストクレスやペリクレスが生きていた時代のアテネではなくなった。
現在の民主主義は、総理大臣・大統領が国政を行なうのと、法律を制定する国会に分かれてる責任の所在を分担してます。これもある意味では、最終的な責任の所在を不透明にする可能性もあります。ある意味、民主主義の限界かもしれないです。この当時のギリシャ全土に覆った人材の枯渇による閉塞感は、自分の国を守ることせず、ただただ生きるためにペルシアの傭兵としての道を選ぶギリシャ人は「そして誰もいなくなった」と言う表現は的を得てます。
王政は統治者の能力により国政は左右されます。その時の統治者の一貫した政略を持って持続する意志が有り、その政略を理解して実行に移す協力者(部下・パートナー)に恵まれると、国は従来の既存体制から改革へ大きく飛躍します。フィリッポスはギリシャの閉塞感の原因を見極め、それを自分の頭で考えながらどうしたら良いのかを考えた。そして国元に戻ったフィリッポスには良きパートナーにも恵まれてマケドニアの台頭に繋がるのです。
そして、ギリシャ全土の混迷と閉塞を感じたのは留学(人質)と言う形で感じたのはフィリッポスだけでは無く、後のローマもそうだったのです、彼らはこの轍を踏まずに柔軟性を持った政治システムを構築していきます。
フィリッポスの跡を継いだアレクサンドロスは言わずと知れた才能に溢れた大王で有り、統治、戦争と類まれなる才能を見せつけて、伝え渡る話は作り話の英雄でなく、実在した英雄ですから、後世の我々を魅了してやまない。アレクサンドロスの話は、本著作に譲るとして、大王亡き後の混迷は、余りにも輝く太陽が無くなった反動でしょうか?それとも後継者に恵まれなかったからでしょうか?
私はココに王政の限界を感じます。著作にも出ますが、王政ならトップダウン型で何でもスピードが命になるメリットが有ります。アレクサンドロスの性格からすれば、何事も自分の頭で考え部下に指示を与える。リーダーの確固たる意志が、優秀な部下に迷いを与えずに確実に指示を行う。しかし、優秀な部下は良き理解者で有るとは限らない。そう言う意味では、アレクサンドロス亡き後の後継者争いでも、アレクサンドロスの意志は政略として残らずに、ヘレニズム世界の文化として残ったのは、感慨深いものです。
一貫した政略が1代限り、短期間の終わらないように、法を政略に用いたのがローマです。法と言う概念が有ったなら、アレクサンドロスが思い描いた国造りは、その後も続いたかもしれないです。その概念を受け継いだのは東地中海でなく、西地中海のローマとは歴史は面白いです。これが短命、長命の分岐点だったのかもしれないです。
そしてもう一度思い出して欲しい。
民衆主義といった何だったのかと?
これが自分の出した答えであるし、この本を読んで他の方も考えて欲しいです。
愚者は歴史を学び、
賢者は歴史を知り、
悪党(英雄)が歴史を作る。
愚者である私にとって、賢者である塩野七生氏が、歴史を作った悪党(英雄)を綴った長編小説「ギリシア人の物語」は、まさに名作です!!
18に出会った文庫に思いを馳せて
私が、塩野七生氏の著作品を知ったのは、10代の霞が関の本屋のアルバイトをしていた時である。文庫売り場の棚に『コンスタンティノープルの陥落』『ロードス島攻防記』『レパントの海戦』の新潮文庫の中世地中海の三部作。ヴェネツィアの歴史を描いた『海の都の物語』は、当時は中央公論社から文庫で発売されてました。(後に、中央公論社は読売新聞社の傘下に入った時に、新潮社に版権が移ります。)
必ず棚に置けば、サラリーマンや公務員系の中高年層の男性が手に取り、そのままレジへと足を運ぶのです。目立つことは無いのですが、確実売れる本として、在庫切れには常に注意したのを記憶に有ります。中国史に興味が有った自分にとって、戦記や攻防のフレーズは歴史小説として面白さを感じて、手に取ったのは自然の成り行きで有り、今思えば、中世地中海を取り上げた書籍は少なかったのが、塩野七生氏の著作に人々が流れたのは必然だったのかも知れず、読めば次を読みたいと思う衝動は当然の成り行きです。
その後に現れる『ローマ人の物語』は、長々説明が長い印象を受けるのですが、その当時ローマ史を扱った書籍も、西洋書の翻訳か、研究科が書かれた専門書でした。そんな堅苦しい書物よりも日本人に分かりやすく古代ローマを説明するために、頭に刷り込むように長々と繰り返し説明したのでしょう。
『ギリシア人の物語』を読み終えて率直に思うのはただ1つ。もし、ifが許されるなら、ここから書き始まる『ローマ人の物語』を読んでみたい。昔のローマ人の物語よりも違ったローマ人の物語が描かれたでしょう。
しかし、歴史にはifは存在しないので、ただただ心の中で思い続けるだけなのです