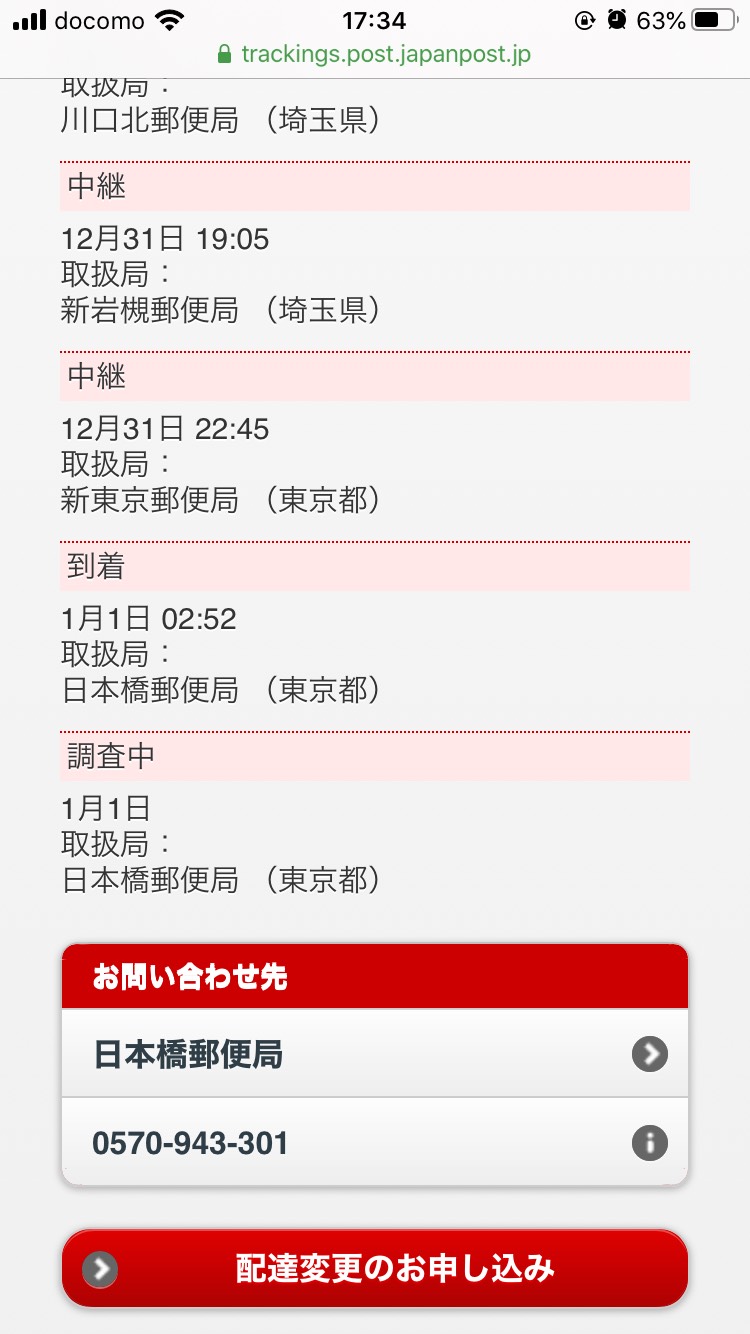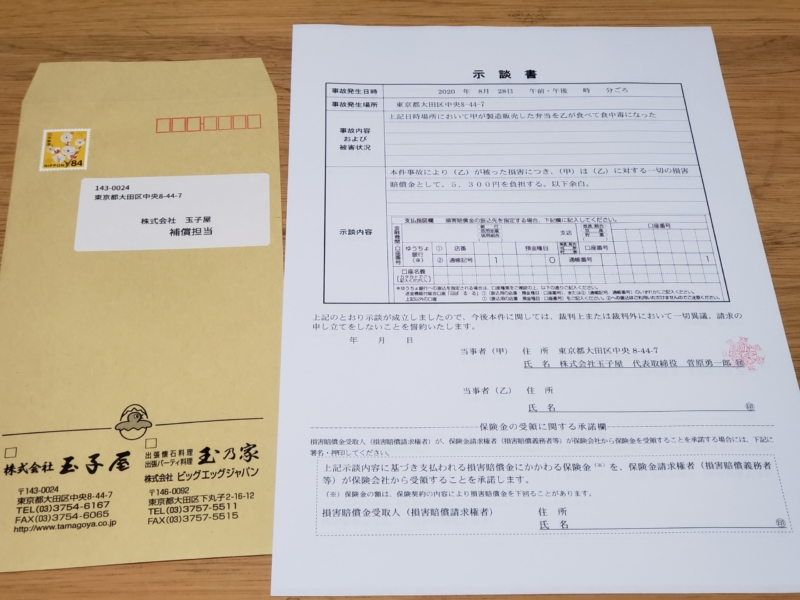東京国立博物館の150周年記念行事として、博物館が所有する国宝89件全ての名品と、明治から令和にかけての歴史を紐解く関連作品等を展示する『国宝展』を観賞したかった。しかし、チケットが手に入らず(涙)。美術館や博物館に目覚めた私は返す刀で、『展覧会 岡本太郎』を観賞しに行って来ました。
『芸術は爆発だ!』、私の頭も爆発寸前!『展示会 岡本太郎』
![]()
『展覧会 岡本太郎』は、東京都美術館で2022年12月28日まで開催されてる。最近、教育テレビで岡本太郎式特撮活劇「TAROMAN」が、あまりにもシュールな展開、でたらめなやり取りで奇獣を退治します。しかも、対決する奇獣も岡本太郎の作品を造形化する等、ネジがぶっ飛んでおり、話題になってます。
![]()
![]()
そもそも、大阪中之島美術館のプロモーションとして作られた「TAROMAN」ですが、ウルトラマンで有名な円谷プロダクションに協力を求めるなど、マニアの間で話題を呼び、上野の展覧会でも特別ブースが出来る反響ぶりです。
![]()
岡本太郎って何者!
岡本太郎は1911年、著名な漫画家だった岡本一平と、歌人で小説家の岡本かの子の長男として生まれた。
18歳で両親と共にパリに渡り、2人が日本に戻ったあとも絵画の勉強と創作活動を続ける。幼少の頃より、「何の為に絵を描くのか」という疑問に悩み続け、絵とは関係のない民俗学まで学ぶようになる。
芸術への迷いが続いていたある日、たまたま訪れた画廊で、パプロ・ピカソの作品《水差しと果物鉢》を見て強い衝撃を受け、「ピカソを超える」ことを目標に、シュールリアリズムに傾倒し絵画制作に打ち込むようになる。
そして29歳のとき、ドイツ軍のフランス侵攻に伴って、それまでに描いた絵や資料を携えて日本に帰国したとされている。滞欧作「傷ましき腕」などを二科展に出品して受賞、個展も開く。しかし、中国に出征している間に自宅は空襲を受け、作品は消失。
戦後は、シュールリアリズムと民俗学がミックスされた独自路線へと進み、多くの作品は発表。岡本太郎の代表作『太陽の塔』、『明日の神話』は、日本国民に「芸術家 岡本太郎」の名は刻まれた。
岡本太郎は、テレビ放送草創期の1950年代から当時のバラエティ番組であったクイズ番組などに多数出演している。独特の風貌に「芸術が爆発だ!」「何だ、これは!」などのフレーズを叫びながら現れる演出で、お茶の間の人気を博すと共に、彼の発したフレーズは流行語となる。
老いを重ねても岡本太郎の創作意欲は衰えず、展覧会出品などの活動を続けていたが、1996年1月7日、パーキンソン病による急性呼吸不全で死去した(満84歳没)。
![]()
岡本太郎の足跡は、色んな文献を拝借すると、こんな感じでしょうか。岡本太郎が発するエネルギーは様々な業界に影響を与えました。しかし、名前は知れども、作品は「太陽の塔」しか知らない私は、展覧会が上野で開催されてると言うこともあり、この機会に観賞させて頂こうと思い、東京都美術館へ足を運んだのです。
![]()
大まかに4部構成に作品が分かれており、1部が戦後から発表された作品。2部が滞仏時代から戦前の作品。3部は、日本の縄文時代、民俗学、そして各国の民俗学からインスピレーションされた作品。4部が『太陽の塔』、『明日の神話』の制作過程について。大まかに分けるとこんな感じでしょうか。
![]()
![]()
展示会の岡本太郎の作品と一目瞭然で分かるのですが、テーマを見ないと何を訴えてるのかが良く分からない。終いにはどの作品も同じように見えてくる。実際には、色が違うだけで立体造形もある。抽象過ぎて、動物なのかすら理解不能で、まさに『なんだ、これは!』の連発である(笑)。
![]()
![]()
しかし、これが2階ブースの滞仏時代に入ると、作風が一変する。近年、フランスで発見された岡本太郎の作品の3点から始まり、初期の代表作『傷ましき腕』、『露店』に『師団長の肖像画』と見てるだけで安心感と親しみ易さを感じる作品へと変わる。特に『師団長の肖像画』を観ると、岡本太郎ってちゃんと肖像画も描けるのかと驚いた。
それは滞仏時代に、「何の為に絵を描くのか」と言う苦悩の中で、試行錯誤を重ねていった過程なのでしょう。はっきりと登場人物を描きながらも、「ピカソを越える」と言う目標が出来たお陰で、徐々に抽象的な作品へと変貌していく様は興味深いです。
![]()
![]()
民俗学のブースになると、岡本太郎が戦後に訪れた日本各地の民俗的な儀式の風景、メキシコの写真が展示されて、奇抜な立体造形の源流が、民俗学からオマージュされて、岡本太郎の思考開花させたように感じます。それでも展示されてる「縄文人」のオブジェ(立体造形)を見ても、人には思えず、怪獣か、宇宙人のように見えます。
岡本太郎の目線から見れば、太陽は顔のように見えるのかもしれない。シュールな考えだが、そこがシュールリアリズムの作風なのだろうか。超現実世界のように感じます。
![]()
![]()
シュールリアリズムとは、日本語に訳すと『超現実主義』。岡本太郎の作品集を観てると、何処が現実なのかと思うのですが、そもそも日本語の『シュール』は物事・言動・体験の様子が「超現実的で・不条理で・奇抜で・難解である」ような場合に用いられます。
そして、シュールは芸術運動であるシュルレアリスム(超現実主義の意味)の略語です。この運動はダダイスムに続いて1920年代に興ったもので、一般にはサルバドール=ダリ(Salvador Dali)の絵画がよく知られます。フロイトの精神分析の手法にも大きな影響を受けており、「意識下の世界を客観的に表現する」ことを理論的支柱にしていました。つまりシュルレアリスムは、あくまでも“超”現実主義なのであって、決して“非”現実主義ではなかったのです(ちなみに前身のダダイスムは“非”合理や“非”道徳を信条としていました)。
![]()
![]()
奇想天外な発想ですが、数学のトポロジー(位相幾何学)のように考えれば、その奇抜な手法や表現も理解が出来るように思えます。
岡本太郎の作品集を眺めてる内に、何処かで同じような作風を見たような気がしてきた。何だろうなっと考えてると、アニメ「エヴァンゲリオン」に登場してくる使徒に似てると気付く。
Google先生に教えを乞うと、サキエル・シャムシエル・ゼルエルをデザインした漫画家のあさりとしおさん。この方は高卒後に公務員を経て漫画家となった方で、得意な宴会芸が 『パイラ星人(岡本太郎デザインの宇宙人)の真似』 という人物で、使徒のデザインにも太郎の影響を受けたと語っています。
現代のクリエイターにも大いなる影響を与えた岡本太郎、彼の過去最大の回顧展である「展覧会 岡本太郎」は、如何に偉大な芸術家で有った岡本太郎と言う人間性や作品集を知る上で、観に行く価値は有ると思います。年明けからは愛知県美術館で3月迄開催されるので、興味の有る方は観に行かれては如何でしょうか。
![]()
![]()