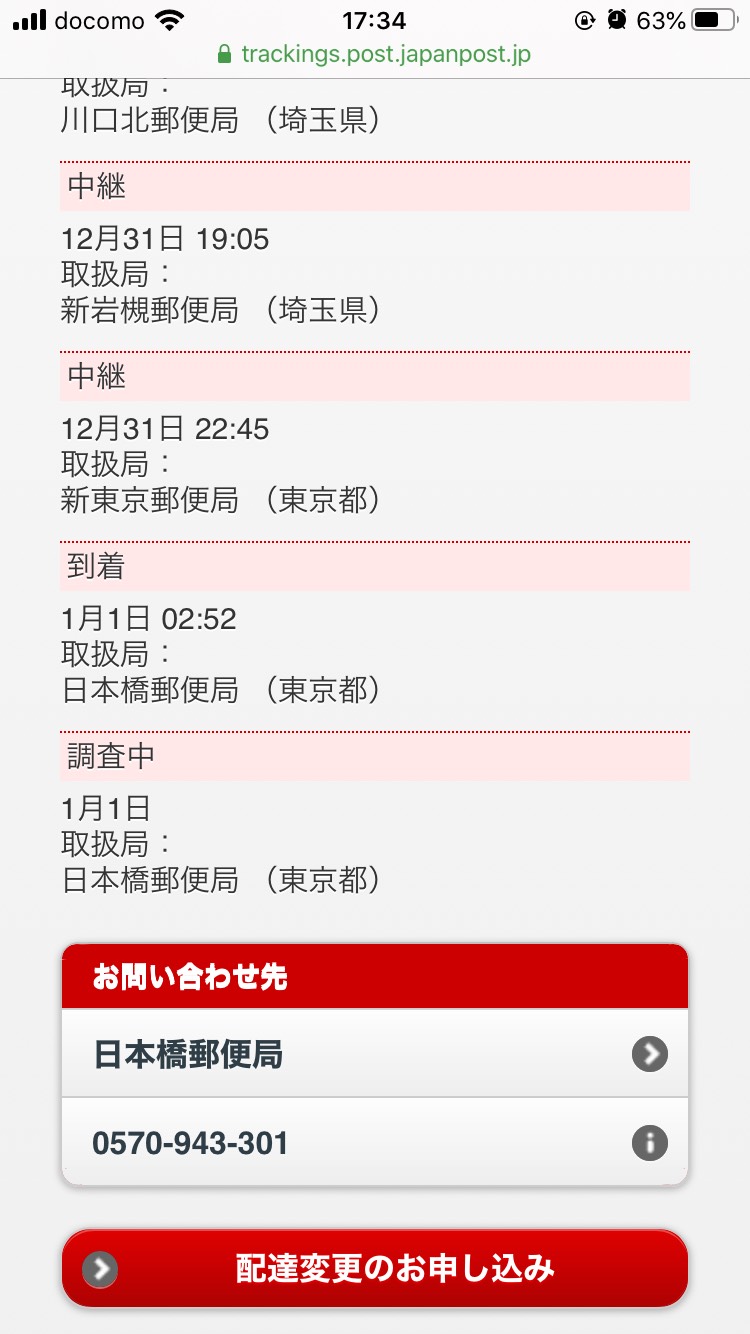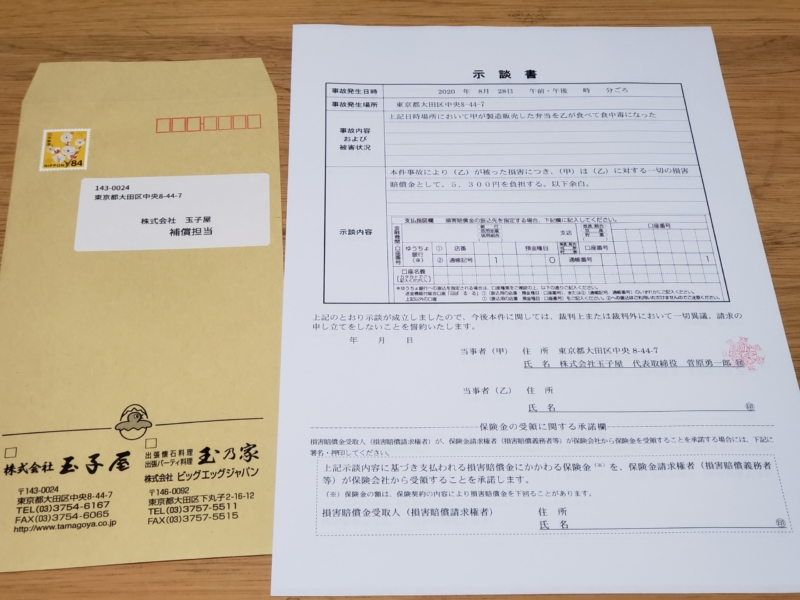検察庁法改正案は、まさかの賭け麻雀というスクープで幕が下りるとは、誰が想像しただろうか!!誰が見ても依怙贔屓の人事を通そうとしてたけど、まさかの本人が人格的にだらしないと来たら、それは国民も怒るしダメダメでしょうとなりますね(笑)「おごる平家も何とやら」そろそろ終わりの時期が近づきつつあるのかも知れないです。
伊豆随一のパワースポット、源頼朝が崇敬した『三嶋大社』
![]()
神池と桜
![]()
伊豆国一ノ宮「三嶋大社」の由来
伊豆国(いずのくに)一ノ宮・伊豆国総社である「三嶋大社」。
伊豆国とは、奈良時代からの令制国の1つで、現代の静岡県伊豆半島から東京都伊豆諸島の地域になります。ある地域の中でもっとも社格の高いとされる神社が“一ノ宮”ですから、伊豆半島の中で一番格式の高い神社は、三嶋大社ということになるわけです。建立は不明ですが、文献によると奈良時代758年に初めてその名が見られます。その後、源頼朝公が源氏再興を祈願した神社としても知られ、「日本総鎮守」と仰がれていた時代もありました。
御祭神は、山、海、農産の神とされている「大山祇命(おおやまつみのみこと)」と、俗に「えびすさん」と呼ばれて商・工・漁業に御利益があるとされている「積羽八重事代主神(つみはやえことしろぬしのかみ)」の、2つの神様を合わせて「三島大明神」とされています。また、事代主命は「宮中八神殿」にお祀りされており、天皇を守護する神様8神のうちの一柱です。現代では、商売繁盛と開運のパワースポットとして、県内外からも多くの参拝者が訪れます。
総門
![]()
神門
![]()
舞殿
![]()
参拝客で長蛇の列
![]()
桜の時期の三嶋大社とパワースポット!!
拙僧にとって、三嶋大社に訪れた最大の理由は、伊豆半島随一のパワースポットと、境内や神池に咲き乱れる桜を愛でる春爛漫の花見。今回三嶋に訪れた最大の理由は、まさに三嶋大社は開運を授かる。俗にまみれてる節操には縁が無いでしょうが!(笑)
訪れた当日は天気は快晴、ほんわかと日差しも暖かく風少なし。境内へと続く参道は、既に参拝者と花見客の往来で凄い人混み、一瞬人酔いモードが発生しそうになりました。桜の時期はバスツアー等の観光客も多くて、三嶋大社周辺の道路は交通大渋滞です。
本殿へと続く桜並木の両脇に神池が設けており、咲き誇る桜を水面が映して、雅な演出です。訪れた人々は思い思いにシャッターを押す音が聴こえて来ました。
参道を真っ直ぐ進むと、総門が有り、そこを潜ると左手に社務所、右手に宝物館。更に桜並木を真っ直ぐ進むと神門が有ります。宝物館には、三嶋大社に伝わる御神宝、文書、資料など多数保管、展示し、北条政子が献上した国宝「梅蒔絵手箱」の模造復元品を常設で展示しています。また宝物館の裏手に神鹿園があり、鹿の愛くるしい姿が参拝者の目を癒してくれるアイドル的存在です。こちらの鹿は「春日大社」(奈良県)から譲り受けた神の使いの鹿でも有ります。
神門を潜ると、年間を通じ様々な神事、奉納行事が執り行われる舞殿が設けて有り、本殿と同じく小沢派による精緻な彫刻が施されてます。舞殿を迂回すると、三嶋大社の本殿が目に飛び込んできます。本殿・幣殿・拝殿、三つの建物が連なる複合社殿で、総けやき素木造りで、伊豆の名工小沢半兵衛・希道父子一派による彫刻は精緻で高い完成度です。本殿への参拝で列で待ってると、本殿の彫刻が施されてるのですが、こちらが他の神社と違って興味深く、通常ならば動植物が掘られてる事が多いのですが、三嶋大社は違って、本殿中央部分の彫刻は、天照大御神(あまてらすおおみかみ)が天岩屋戸(あめのいわやど)から出てくる様子を表しています。
向かって右側の彫刻は、奈良時代の学者・吉備真備(きびのまきび)が囲碁をしている様子です。遣唐使として唐に渡り、暦学の書を持ち帰ってきた方として知られています。この彫刻は「知恵」を表しているとのこと。
向かって左側の彫刻は、源三位頼政がヌエ(日本で伝承される妖怪)を退治した様子。この彫刻が意味することは、「勇気・決断」といいます。これらの彫刻は、伊豆の名工小沢半兵衛・希道父子一派で「知恵」と「勇気・決断」の両輪があることが大切ということを意味してます。
本殿では厳かに神前結婚式が行われてました。ちなみに、神前結婚式の費用って幾らなのだろうと調べたら、15万もするそうです。これが高いのか安いのか、男やもめには分からないのが恥ずかしい。しかし、こんなに参拝客が来てる前での結婚式ってある意味凄いなって思いました。参拝者の祝福も受けながらの結婚式は、神前結婚式ならではのサプライズ演出でしょう。
そんな俗な考えを抱きながら、無事に本殿の参拝は無事に終了。境内での神池の桜や鯉を眺め、天然記念物に指定されてる金木犀(咲いてませんがw)を見学しながら、三嶋大社の歴史を感じる奥床しき風情を堪能しました。
本殿
![]()
本殿上の彫刻
![]()
金木犀![]()
神池
![]()
![]()
![]()
番外編 みしまコロッケは美味しかった!!
水の都・三島のオススメの食べ物といえば、「鰻(うなぎ)」
しかも、三嶋大社の神のお使いも「鰻(うなぎ)」です。鰻が神のお使いとは珍しく、相場は鹿だろうと思います。全国的に調べてみると、三島に限らず鰻を神使いとしている地域に岐阜県、東京都日野市、山梨県の一部地域などがありますが、鰻を食べない地域として知られています。つまり、神のお使いなので食べるのはご法度なのですが、三島も例外ではなく、江戸時代末期までは三島も鰻を食べるのはご法度でした。三島で鰻を食べ始めるキッカケとなったのは、幕末に薩摩と長州の兵隊たちが三島宿に泊まった際に、鰻を手あたり次第捕獲し、かば焼きにして食べても神罰があたらなかった様子を見たとか。それ以来三島では鰻を神使いとしているにもかかわらず、街中には美味しい鰻が食べられる飲食店が多数存在する、「三島の鰻」として全国的に有名なったのです。
それでは拙僧たちも鰻を頂こうかと思ったのですが、既に昼食を食べた後で、参拝後に鰻を食べる時間もないと来た、残念次回訪れた時にでも頂きましょう!!
それでも少し小腹が空いたので、周りを見渡すと目に飛び込んできたのが「みしまコロッケ」の看板が、、、!!ご当地グルメかと思いGoogle先生で調べてみるとみしまコロッケに使用するじゃがいもは、三島馬鈴薯だけを使用することが条件のコロッケです。これは一度どんな味か食べてみたいと思い、並んで買おうとしたら「今揚げてるの少々お待ちを!!」の声がw
揚げたてのコロッケを食べるのも良いだろうと思い、5分ほど待ってると揚げたてのみしまコロッケが登場!!何度も繰り返しますが。みしまコロッケの中に入れる三島馬鈴薯以外の具や形はそれぞれのお店の自由です。肉や玉ねぎを入れたりパンにサンドしたり、お洒落にアレンジはOK!!お店によっていろいろなみしまコロッケを召し上がること出来ます。拙僧が頂いたみしまコロッケはシンプルに三島馬鈴薯のみ。でも、これがじゃがいもの甘味と素朴さがマッチして、とても美味しく頂きました。境内で食べるのはバチが当たりますので、少し横の休憩所辺りでテイクアウトで頂くのも良いでしょう。古き歴史と新しいモノを巧みに取り入れて進化する三島の街の一部を見たと思います。
![]()
![]()
![]()